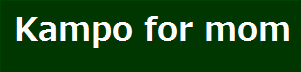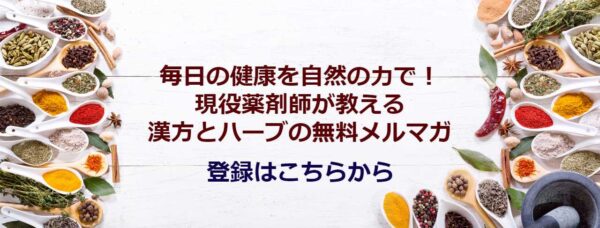漢方薬って、土瓶になんだかわけのわからない材料をいれて、ぐつぐつと煮たもの。
不思議なにおいに、苦くて渋い味。
そんなイメージの漢方薬。
いったい漢方薬って、なにからできているとおもいますか?
漢方薬は2種類以上の生薬が組み合わさってできたもの
なんとなく、薬草のイメージがありますよね。
確かに、植物の根っこや葉っぱ、実が使われることが多いです。
他にも、動物や鉱物もつかわれます。
変わったものだと、
蝉退(せんたい:セミの抜け殻)や竜骨(りゅうこつ:化石の骨)、牡蠣(ぼれい:カキの貝殻)といったものもあります。
こういった漢方薬の材料のことを生薬(しょうやく)といいます。
生薬は、自然にあるものを乾燥させて、<そのまま>で使います。
病院でもらうお薬(西洋薬)は、
植物から、薬として効果がある有効成分だけをとりだして、薬にしています。
ひとつのお薬=ひとつの成分です。
なので、効きめがパワフルになります。
ただ、シャープに効く反面、副作用がでることもあります。
漢方薬の生薬の組み合わせで効果がでたり、副作用が少なくなる
漢方薬は、材料の生薬を2種類以上をくみあわせてできたものです。
使われている生薬、それぞれに役割があります。
そして、組み合わせることで効果が生み出されます。
例えば、知名度ナンバーワンの葛根湯(かっこんとう)でみていきましょう。
葛根湯は、7種類の生薬からできています。
葛根(かっこん)=くず
麻黄(まおう)
桂枝(けいし)=シナモン
芍薬(しゃくやく)
生姜(しょうきょう)=しょうが
大棗(たいそう)=なつめ
甘草(かんぞう)
葛根は、くず餅のくずの根の部分。
桂枝はシナモンの樹皮、生姜はしょうがを乾燥させたものです。
大棗はなつめの果実。
とっても甘いので、薬膳スィーツにも使われたりしています。
生薬というと、難しそうですが、意外と私たちの身近なものも多いんですね。
葛根湯の生薬の組み合わせの意味は、こんな感じです。
葛根でこわばりをとる。
麻黄+桂枝の組み合わせで、汗をかかせる。
芍薬が痛みをとめる。
というようにはたらきます。
生姜、大棗、甘草は、胃薬のような役割をしています。
こんな風に、漢方薬に使われている生薬の種類や量には、理由があります。
病気に対する効果を高めて、
副作用がより少ない安全な薬になるようにと設計されているんですね。
ここが西洋薬との大きな違いだとおもいます。
長い長い歴史と経験を積み重ねて、現在に受け継がれてきた漢方薬。
まるで現代を生きる私たちへのプレゼントのようです。
いろいろな自然の恵みと古の人々からの知恵からできている漢方薬、
上手に使って、家族みんなで笑顔で元気に過ごしていきましょう!